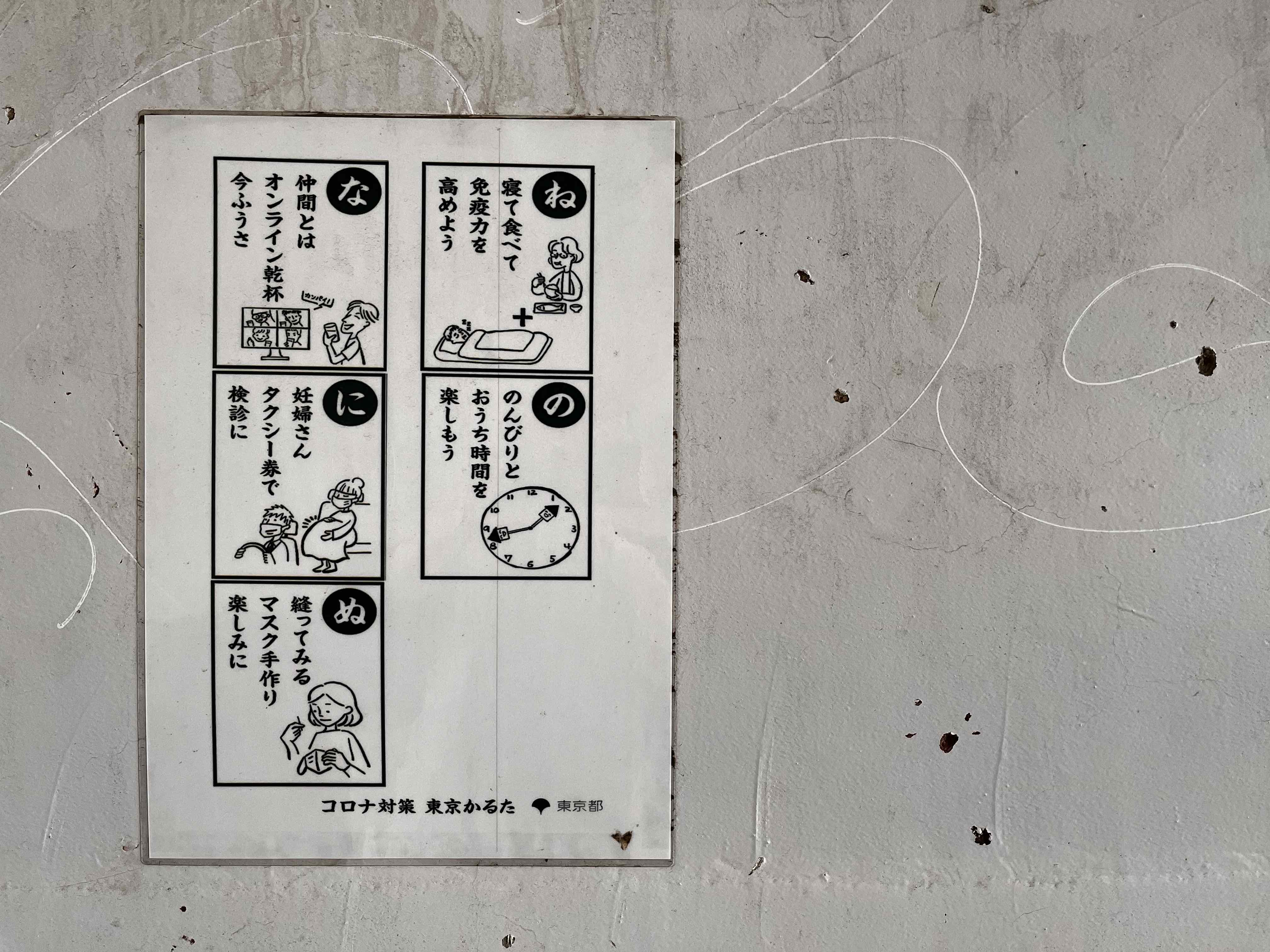
新世界、新生活、シン怒濤
2024.03.22 – 2024.04.12 東京・静岡・埼玉・千葉
朝日新聞の「文芸時評」の第12回をぶじに仕上げ、つまり1年間を走り抜けて、今年6月3日に締め切りを設定した新しい作品(小説である)の準備に入り、新たなコラボレーションのプロジェクトの顔合わせを終えて、そして、ここには書かないが、とある〈他者の作品〉に予想を超えた日数(……超えてほしくなかった……)関わることになり、しかしながら新作の準備はいつも頭の片隅において、そして群像新人文学賞の最終候補作を1度読み、さらに1度読み、選考会に臨み、というのをやりながら、第13回の「文芸時評」のための読書も進める、ということをやっていたら、移動時間がどうしても不足して、結局は東京都内に泊まることにもなる、という新生活がじつにシン怒濤で、そういう新世界を私はいま生きている。
が、大きなことをふたつ、みっつと獲得しつづけてもいる。
これは群像新人文学賞の選評にも書いて、来月号の「群像」に載る文章の展開形でもあるのだけれど、そういうのを少し今回の「現在地」では書く。ある挑戦をしたい、と考えている作品は、その挑戦をみごとに達成した時に、じつは単純に高く評価されるとは限らない。〈完成品〉こそはキズが目立つ。だから挑戦などしていない作品よりも下に見られる、ということが起きる。これは私自身が、ある同業の方から言われたことでもある。というか、それは保坂和志さんだった、その言葉には私はいまも励まされつづけている、と深い謝意をここに記したほうがよい。もしも、誰かが大いに賞讃するのならば、そこには、誰かから大いに批難される可能性が、または冷遇される可能性が、つねに同時に/いっしょに孕まれている。この表裏一体をどう考えるか。それからもうひとつ。今日ここに書きたいのはこっちだ。
ある世界を描く、という行為は、その世界を〈現実〉のように迫力をもって描く、という次元に達した時に評価される。現代を描写する際もそうだし、過去のいつかを、あるいは異世界を描写する際にもそうだ。しかし、そこに〈現実〉の迫力を出した時、私たちは〈歴史〉に触れられるのか? 歴史とは鳥瞰である。ひとつひとつの〈現実〉から離れて、串刺しにして見る、等の感受性が要る。または飛び石のように跳んでみる精神の肉体性が要る、とも言える。「精神の肉体性」とは矛盾だ、と指摘するならば指摘すればよい。結局、ひとつの〈現実〉に縛られてしまったら、そこからは離れられない。つまり、中世だの古代だのをリアルに書くことはできる。しかし、リアルにするとは〈現実〉化するということで、その力量は大したものだけれども、そこから〈歴史〉は起ち上がらない。要するに「第二の2024年(の日本、その他)を書いているに過ぎない」わけだ。そんなものは〈歴史〉を駆動させない。
ここから何が言えるか?
きちんと〈歴史〉を駆動させている小説は、……いいや、ここでは「きちんと〈歴史〉に接触している小説は」と言い直そう、そういう作品は、ひとつひとつの時代や世界には、もしかしたら〈現実〉感をもって触れられていない。それはまさに目立つキズである。しかし、たとえば西暦1221年を、これは和暦だと承久3年であってこの年にこそ承久の乱が勃発するが、そこをきちんと〈現実〉の迫力で描出できたとして、承久の乱を題材にしているのに〈歴史〉に接触していない文学が、どんな〈力〉を持つのか?
私はそこを考える。私はそれを考えているのだ。
そこまで考えたうえで、自分は最終的に、評価としては表裏一体の〈現実〉と〈歴史〉を真のカオスに落とさなければならない、とも考えている。これは野心である。つまり〈歴史〉に触れているのに〈現実〉を起ち上げてもいる、そうした境地に至れるか?
いまの自分には無理だ。まだ。できない。しかし真のカオスとはシン怒濤のその何枚かの薄い皮膜の向こうに、ちゃんと在る、と感じられて(も)いる。となると、そこを当面のゴール視して、私は進まなければならない。何年かかるだろうか? 私はザッと計算はした。目標は2年半だ。この世界の経済状況が邪魔をしなければ、私はそのような期間を費やして、カオスまんまの作家に化ける。ま、やってみますわ。

